未来の地球を守るために、今できること〜ごみ減量×私たちの選択〜|静岡市ごみ減量推進課

静岡市のごみの現状を知る

静岡市ごみ減量推進課を訪問したのは、環境問題に関心がある高校生たち。
中学校で学んだことをきっかけに、もっと知りたいと思い、高校の探究テーマにしたいと考えている生徒もいました。
職員さんから静岡市のごみの現状について、そして対策について、データや写真を見ながらお話を伺いました。
静岡市ではこれまでプラごみの回収をしていなかったのですが、プラスチックリサイクルに関して市民の方にも段階的に協力していただくために、製品プラスチックの分別回収を始めました。
どうしたら分別してもらえるのか…知ってもらう、周知をさせることがごみ問題の一番の課題ですね。そのために学校や公民館などを訪問して出前授業を開催したり、イベントを開催したりと、職員さんが頑張る姿を知ることもできました。
人々の意識で変わる、海洋ごみ
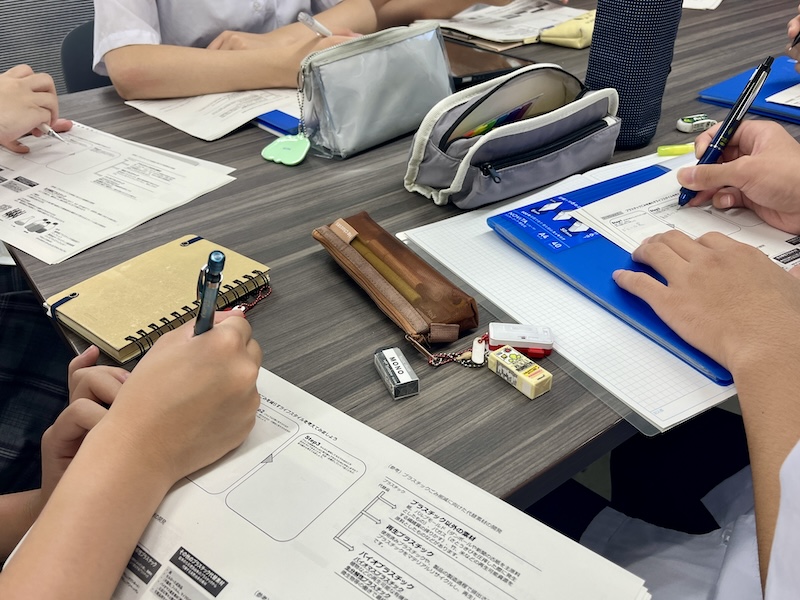
昨今話題となっている海洋ごみについても、詳しくお話を伺うことができました。
海洋ごみ=海に漂うごみですが、海から発生する訳ではありません。
ここでは、ごみは私達が暮らすエリアから出ているという事例をお話くださいました。
例えば、ポイ捨てはもちろんですが、指定のごみ捨て場に出したものでも、しっかりネットの中に入れていなかったりすると、風で飛ばされ川に流され、海に辿り着いてしまうのだそうです。
ごみの出し方、捨て方を意識するだけでも、海洋ごみは大きく変化するのだと。
プラスチックが日光や海水で分解され小さくなり、それを魚が餌と間違えて食べ、その魚を私達は食べる・・・負の循環ですね。
巡り巡って海洋ごみは私達に影響があると考えてみると、とても怖いと感じました。
これから私達にできること

最後に、「プラスチックごみを減らすライフスタイルを考えてみましょう」というテーマで2つのグループに分かれてワークショップを実施しました。
1.私達の身の回りで使われているプラスチック製品を書き出してみよう
2.その中で無くせるもの、代替品に変えられるものを考えてみよう
3.自分達にできること、社会や企業ができることを考えてみよう
ステップ形式で考えるワークショップは順序立てて考えることができるので、グループ内でたくさんの意見が出ていました。
参加した高校生からはこんな意見がでました!
・もっとごみについて話す機会を増やす
・リサイクルを身近に感じ、楽しいと思えるような施策を考える
・SNSを活用して若者の関心をアップさせる
・リサイクルボックスの場所がわかるアプリをつくる
これから私たちにできることは、たくさんありそうですね。
2025年実施
Reported by Misako Kameyama